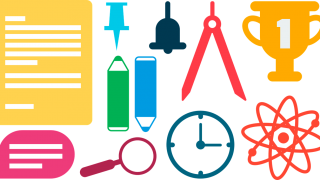小学生の社会科はどう勉強すればよいのか悩みますね。
中学受験はしない予定。休日に親がみるスタイルの自宅学習派のわが家の勉強法をお伝えします。
小学生の社会科はどうやって勉強する?

算数や英語なら、塾や教材も多いけど…。低学年のうちは社会科はお遊びみたいなもんじゃないの?と正直思ってました。
子どもに勉強を教えていても、いざ社会科となるとどうしたものか困ってしまいませんか。私は悩みました。だって、情報がなさすぎですもの。
算数や国語は問題集や参考書も数多くあります。ところが、社会科の参考書や問題集となると、地理や歴史の暗記ものばかり。それも、小学5,6年からで中学受験用の高度な内容のものが中心です。中学受験をしない身としては、ちょうど良いレベルのテキストが見つからないのです。
さらに、社会科は教え方でも悩みます。国語では漢字などは暗記に頼らざるを得ませんが、論理的な文章の組み立て方や、気持ちを伝える表現方法など教える切り口はいくつもあります。算数でも、数や形のセンスをみがくお手伝いは自宅でもできます。ところが、社会科となると「地理」と「歴史」を暗記する…というイメージしかわかないのではないでしょうか。子どもたちはどんなことを学校で教わるのでしょう。
小学4年生、小学5年生で学ぶ社会科の内容

塾か通信教育か?
今うちの子どもは小学4年生で、住んでいる県の各市の特徴や、公共施設、商業施設の役割などを学んでいます。実際に職場見学をさせてもらったり、観光地のことを調べて発表したりという具合です。いわゆる本格的に成績にからんでくる社会科は5年生くらいから。5年生では地理ですね。6年生でのヤマは日本史です。
それぞれの学年の単元を例にみてみましょう。
5年生 社会科
1.日本の国土
国土の地形や気候の概要を、自然条件と人々のくらしにからめて学びます。
2.食糧生産
生産者と消費者の視点から学びます。
3.工業生産
日本を支える各工業について学びます。
4.情報
情報ネットワークの活用や、情報リテラシーについても学びます。
5.自然環境
自然環境の大切さとともに、自然災害についても学びます。
6年生 社会科教科書
1.日本の歴史
古墳時代から戦後まで。
博物館や資料館への見学や、戦争体験者に話を聞くことも。
2.くらしと政治
自分たちに身近なものとして考えられるように、社会保障などを学びます。
3.世界とつながる日本
日本とは異なる文化や習慣を理解し合うことの大切さを学びます。
(参考:光村出版の教科書)
「社会科は暗記だけの教科」というイメージは過去のもの
ざっと眺めて、私たち親世代がイメージする社会科とちょっとちがいませんか。今の社会科は単なる暗記一辺倒では歯が立ちそうにありませんよね。新しい大学入試が刷新されるように、すでに小学生の学ぶ内容も変わってきています。
意識の高い親御さんにはすでに周知のことかもしれません。私にいたっては、自分の子どものころの社会科とずいぶん変わっているなと驚かされました。今でこそ日本史好きの私ですが、学生時代は歴史が苦手で嫌悪感すらもっていました。徳川だけで名前も似たような字面で何人も将軍がいるし、肖像画もおじさんばかりで見ていてさっぱりつまらない…。土方歳三あたりはイケメンですが。地理だって、行ったこともない場所の地名や産業をひたすら覚えるのみ。もはや修行以外のなにものでもありません。
もちろん、全く暗記を避けて通れるわけではありません。最低限、覚えなくてはならないことはあります。都道府県の位置や名前、歴史上重要な年号などは、大人になってからも教養として必要です。ただ、それを覚えるのは何のためなのかにちょっと意識を向けるだけで、子どもの社会についての興味印象はがぜん変わってきます。
「社会科」は未来を生きる子どもたちの武器になる
子どもが生きていくうえでかかわっていく「社会」。
多様な人が集まって機能する社会を理解するために、ヒントとなるパーツが「地理」であり「歴史」である「公民」なのかなと。今の子どもが大人になるころには、もっともっとグローバル化も情報化も進みます。いろいろな情報を自分ごととして咀嚼して判断する力が必要です。そして、自分とは異なる価値観をもった他人と協力して問題を解決していく能力が求められるはず。企業の求める人材などからすると、あながち間違ってはいないでしょう。
せっかく、社会の学習にも少なくはない時間を費やすのです。どうせならば、子どもの血肉となる学びにしたいものです。
最初から暗記に走ると辛いし無駄が多い

暗記カード
社会科は好き嫌いがはっきり分かれる教科です。
物語で興味をおぼえた戦国武将がいれば、大人が教えなくても勝手にどんどん周辺知識を集めていきます。地図が好きな子ならばゲーム感覚でつぎつぎ政略していきます。そんな子は社会の時間を待ち遠しく思いますが、とりたてて興味のもてなかった私のような子どもは苦手意識をもったまま学年が上がっていくことになります。悪いことに、小学校で苦手意識を植えつけられると中学になっても挽回することは難しいのです。
暗記教科だから、受験が近づいたら一気に覚えれば良いだろうというのも危険です。受験期にはほかにも覚えることが山ほどあります。もともと嫌いで素地もないところに、大量の情報が一度にきてもそれは無理というもの。
何でも同じですが、小学生のうちに土台をしっかり育てておくことが大事です。受験組でなければ、地理や日本史の細かな枝葉末節まで覚え込む必要はありません。小学生の日本史ならば、ざっくりとした古代からの流れを掴んでいれば上出来です。最初から完ぺきを目指すと、挫折します。歴史なら大枠で流れを掴んでおいて、中学になってから細かな部分を肉付けしていくイメージです。キーワードだけその場しのぎで覚えても、自分の血肉とはなりません。急がば回れ。地理でも歴史でも、全体像を思い浮かべながらコツコツと学んでいくに限ります。
長期的な視点で「社会科」に興味をもってもらう
机にかじりつくだけが勉強ではないです。幼いうちこそ、身の回りにあふれるちょっとした疑問に目を向けること。ニュースで見た自然災害でもかまいません。どうして災害が起こったのか。地形が関係するのはなぜか。気になったことを、親がほんの少し掘り下げてあげるだけでも、子どもの記憶のはしっこに残ります。後々授業で取り上げられたときに、「あのときのことだ!」と記憶が結びつきます。
勉強と堅苦しく構えなくても、観光でお出かけした先でお城を見に行ってもいいです。帰ってきてから、いつの時代の誰の城かを調べるだけでもおもしろいもの。戦国武将が登場するゲームもあります。子どもが好むものなら、何でもいいです。
ある程度の年齢になったら、歴史のドラマや漫画を紹介してみてください。今まで散らばった点の知識が、線となってつながります。一気に理解が進みます。面白さがわかれば、子どもは自分から知識を吸収していきます。
口で言うのは簡単で、うちもどうなるかは神のみぞ知るですが、環境を整えておくことだけはできるかなと。本当の意味で、親ができるサポートはそれくらいかもしれません。
具体的な社会科の勉強法
具体的にどんな勉強法があるでしょうか。
都道府県をまず覚えたいのなら、ニュースや会話の中で出てきた地名を、逐一地図で探すというのがおすすめです。地理カルタも家族でやると盛り上がります。なかでも、直接県名を出さずに周辺情報で攻めてくる読み札のものが勉強になります。うちでは最初100均のものを買ってみたのですが、やはりちゃんとした出版社の方がよくできていました。
旅行に行ったら、楽しかったで終わらせずにもう一歩踏み込んで知見を広めてみる…。小学生のうちほど、親のサポートが活きてきます。
とはいえ、親も忙しいですので使えるものは使いましょう。
個人的には、公的なイベントなどをよく利用しています。定番の社会科見学から、さまざまな職業の人に直接教えてもらう講座、国際交流イベント…。親も楽しいです。子どものころ勉強できなかったぶん、便乗してます。
また、学年が上がり学習という面で強化しくなったならば、自宅でできる通信教育が便利です。わが家ではスタディサプリを2年近く利用しています。月1000円なので、ドリル1冊と思えば安いものです。最近では社会科が気に入っているのですが、各県の特徴を世間話的に教えてくれるので小難しくなく頭に入ってきます。
意外ですし、地形もいっぺんに記憶に残ります。人に言いたくもなるような授業なので、親もたまにいっしょに聞いています。
歴史は何といってもマンガですね。子どもがとっつきやすく、全体像を把握しやすいという意味からも進めやすくなっています。
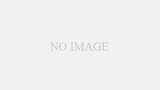

小学生のうちから楽しく社会科に親しんでもらおう
偉そうに講釈していますが、わが家も現在進行形で子どもの勉強については模索中です。子どもの成績が抜群に優れているわけでもありません。ですが、大学に入って燃え尽きてしまうようにだけはなって欲しくないのです。
できる限り、押しつけではなく将来的に子どもにとって役立つ知識や能力がつけばと試行錯誤しています。親自身も、子どもが今どんなことを学んでいるかをまず理解し、いっしょに成長していければと思っています。
小学生のうちは興味関心の芽を育て、高学年からは学習漫画や通信教育も併用して理解を深めていきたいです。家庭学習派のみなさん、時間のやりくり苦心すると思いますが、お互いがんばりましょう!
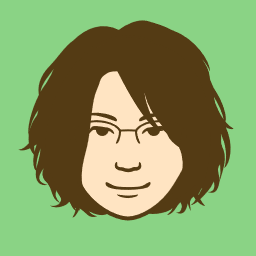
受験対策・時事問題に強くなるなら新聞も! 国語力も身につきます。